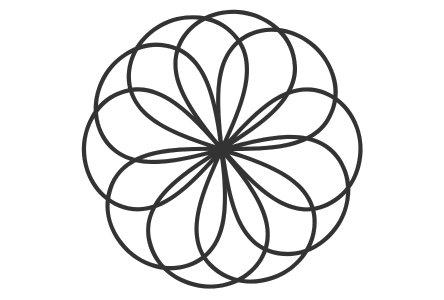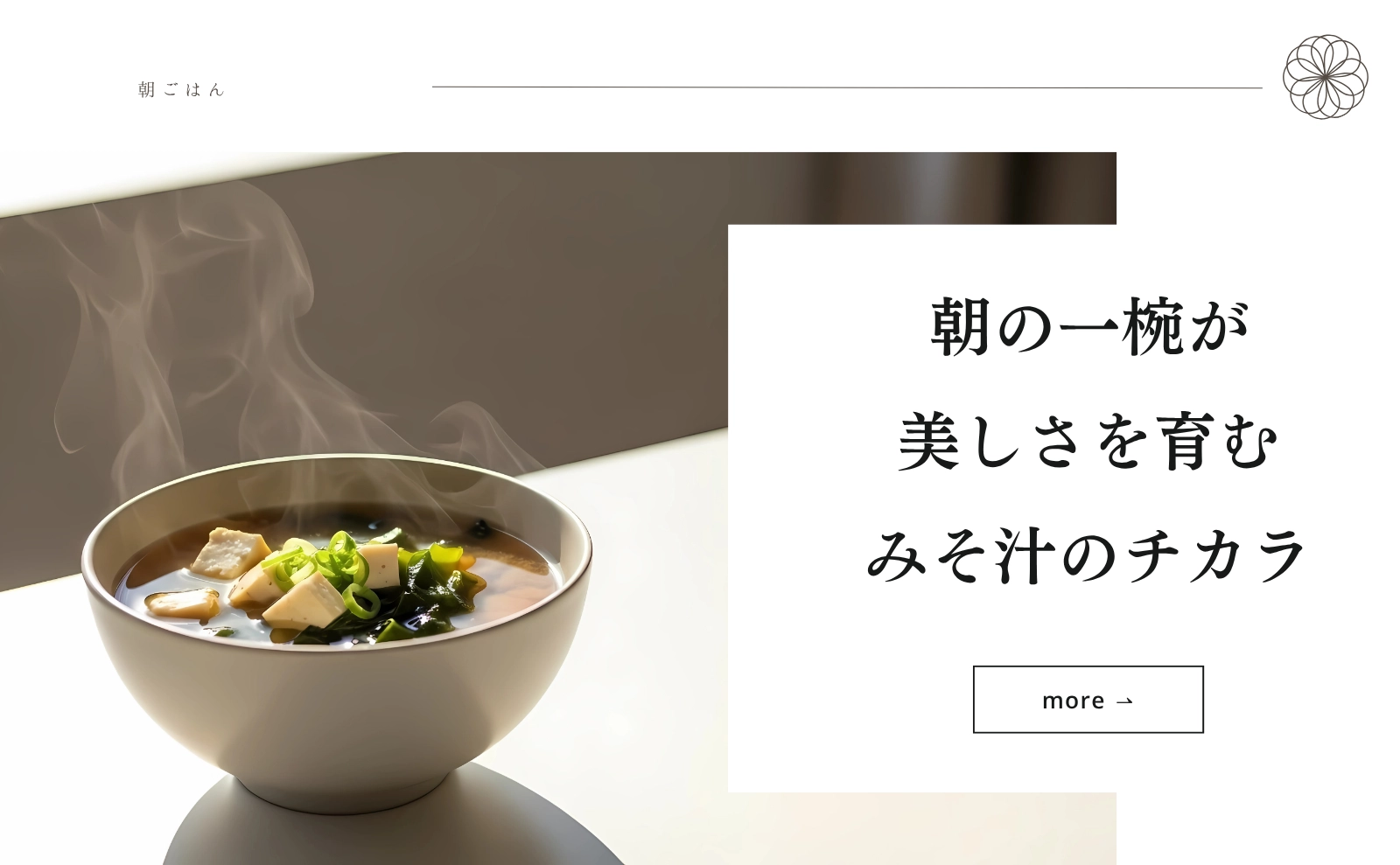体にいい油の選び方は?

「油は太る」「体に悪い」——
そんなイメージを、いつから持つようになったのでしょうか。
確かに、質の悪い油は体内で炎症を引き起こし、病気のもとになることもあります。
でも実は、油は私たちの体に欠かせない“潤い”であり、心とからだの健やかさを支える大切な三大栄養素のひとつなのです。
細胞膜やホルモンの材料となり、脳や内臓・肌にまで深く関わるからこそ、
“どんな油を選び、どう使うか”は、私たちの毎日にそっと影響しているのです。
この記事では、中医学と現代栄養学の視点から、からだに寄り添う「油の選びかた」をやさしく丁寧にご紹介します。
良質な油を選ぶ3つの基本
油は見た目ではなかなか判断がつきにくいもの。だからこそ、「選び方の軸」を知っておくことが大切です。
- 圧搾製法のものを
「圧搾一番搾り」と記載されている油は、化学溶剤を使わず、低温でゆっくり丁寧に搾られています。
そのため、熱に弱いオメガ3やビタミンEなどの熱に弱い栄養素がしっかり残っています。 - 遺伝子組み換えでない原料を
「NON-GMO」や「有機」などと表記されている信頼できる製品を選びましょう。体内に取り入れるものだからこそ、できるだけ自然な原料を選ぶのが理想的です。 - 精製度が低く、酸化しにくいものを
見た目が透明すぎず、自然な色や香りが残っている油は、栄養が豊富で酸化しにくく体にもやさしい証拠です。
目的別に選ぶ、からだを整える油たち
油には、それぞれ異なる特性があります。
自分の体調や目的に合わせて“油を使い分ける”という視点を持ってみましょう。
オメガ3脂肪酸で「炎症体質」をリセット
えごま油/アマニ油/インカインチオイル
- 脳の働きや血流を整える
- 認知機能や血管の健康を保つサポートを
- 納豆やサラダに「加熱せず」にかけるのが基本
補足:現代人はオメガ6(サラダ油・ひまわり油・コーン油など)を摂りすぎる傾向があり、オメガ3とのバランスが崩れやすくなっています。
加熱調理に向く「酸化に強い油」
オリーブオイル/こめ油/ごま油
- 抗酸化成分が豊富
- 香りや旨味もあり、使いやすさ◎
- 炒め物・揚げ物・ドレッシングなどに幅広く活用
中鎖脂肪酸で「即エネルギー」に
ココナッツオイル/MCTオイル
- 体脂肪になりにくく、代謝をサポート
- 朝のコーヒーやスムージーにひとさじ加えて◎
避けたい油、注意したい使い方
知らずに取り入れてしまうことも多い“避けたい油”。
からだに余計な負担をかけないためにも、ぜひ意識してみてください。
×トランス脂肪酸(マーガリン・ショートニング)
動脈硬化や心疾患リスクが高く、海外では規制も
パンや菓子類に多く含まれるため、表示を要チェック
×高温で繰り返し使った油
揚げ物の油を使い回すと酸化が進み、過酸化脂質のもとに
色・臭い・泡立ちに違和感を覚えたら、新しい油へ
×安価で精製度の高いサラダ油
栄養価が乏しく、酸化しやすいものも多いため、常用には不向きです
油の保存にもひと工夫を
- 遮光瓶に入れ、冷暗所で保存
- オメガ3系の油は特に酸化しやすいため、開封後は冷蔵保存が必須です。
中医学から見た「油」の役割
中医学では、油は単なる栄養ではなく「潤い」を補う重要な存在とされています。
良質な油の摂取がおすすめの方
特に次のような状態にある方には、良質な油の摂取がすすめられます。
- 乾燥肌・便秘・のぼせ・寝汗がある
- 更年期や月経の乱れが気になる
- 疲れやすく、気持ちが落ち込みやすい
油ごとの中医学的な働き
オメガ3系の油(えごま・アマニ)
→ 血の巡りを促し、気血のバランスを整える
ごま油・オリーブオイル
→ 「内熱(のぼせ・イライラ)」をやわらげ、肌や腸の乾燥にもやさしく作用
「潤いを足す」というケアが、じわじわと心と体に効いてくるのが中医学ならではの知恵です。
おわりに|明日の調子は、一滴の油から
私たちの体は、思っている以上に“油の質”に影響を受けています。
とくに現代の食生活は、オメガ6脂肪酸や飽和脂肪酸が過剰になりやすく、体内のバランスが崩れがち。
だからこそ——
オメガ3、オメガ9系の油を上手に取り入れることが、内側からの整えに繋がっていきます。
最初の一歩は「ひとつの油を変えてみること」から。
- いつものドレッシングを変える
- 炒め油を見直す
- 朝の納豆にオメガ3をひとさじ足す
そんな“小さな実践”こそ、習慣をつくる第一歩です。
「油は避けるもの」ではなく、
「自分を整えるために、選ぶもの」。
今日の一滴が、未来のわたしの肌、心、代謝を支えてくれる。
そんな視点で、油と向き合ってみてくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました。